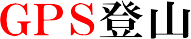槍ヶ岳へのあこがれは、常念岳から眺めた槍ヶ岳の容姿に感激した時からです。そのかっこういい山頂に、是非立ってみたいという思いに駆られたのを今でも覚えています。今回は一緒に登りたいという息子と3人での山行です。
槍ケ岳は日本アルプスの十字路と言われる様に、中房温泉から大天井岳経由の表銀座縦走コース、岐阜県側からの新穂高コース、穂高岳からの縦走路、そして私達が登った横尾から槍沢経由の上高地コース等、いろいろなコースがあります。富士山に次ぐ「一度は登ってみたい山」というだけあって家族連れの登山者が多いです。
1日目は、上高地バスターミナル、明神、徳沢、横尾、と約11kmの平坦な道をひたすら歩き、横尾で穂高への吊り橋を左に見て直進すると、いよいよ槍ケ岳へのコースに入ります。一ノ俣谷、二ノ俣谷を渡ると今日の宿泊地、槍沢ロッヂです。
2日目は、槍沢ロッヂを早朝に出発。槍沢ロッヂから槍ヶ岳までは5.9kmの登りです。
槍の穂先が大きくなる手前に「坊主の岩屋」があります。槍ヶ岳開山の幡隆上人が修行の時に泊まったと言う岩屋です。さらにガレ場やザレ場が続きますが、槍の穂先がだんだん大きくなっていくのを仰ぎ見ながらの登りは最高です。殺生ヒュッテへの分岐を過ぎると、もうすぐ槍ヶ岳山荘です。
<<坊主の岩屋>>
槍ヶ岳初登頂・開山をなしとげた念仏行者幡隆がそのつど利用した岩屋。幡隆は五回槍ヶ岳登山をしたが、天保5年(1834)の第四回登山の時は、この岩屋で五十三日間も篭り、念仏を唱えたという。
 後方に常念岳
後方に常念岳槍沢辺りからは、後方に常念岳が見えるようになりました。
槍ヶ岳山荘の手前あたりから、ガスがかかり始め、槍の穂先を眺めることができません。
槍ヶ岳の花達・・・花の時期に登ることができ、たくさんの花に出会えました。
槍ヶ岳山荘に到着後、一休みしていよいよ槍の穂先に登ります。山頂へは、途中から登りと下りに分かれており急な岩場を、鎖やはしごを使って登ります。
槍ヶ岳山頂は狭く、幡隆上人が背負って登ったという阿弥陀如来・観音菩薩・文殊菩薩が安置された場所なのでしょうか?小さな祠があります。その前は記念写真を撮る人達で賑わっていました。
3時頃は晴れ間が期待できそうと言うので再度、穂先を目指します。期待どおり大天井岳や常念岳や蝶ヶ岳を眺めることができました。
3日目は、朝4時に起床、早めの下山の予定でしたが、御来光が拝めそうなので少し待つことにしました。東の空が次第に明るくなり、待望の日の出の瞬間には、多くの登山者が歓声を上げていました。
槍ヶ岳山荘を後に、槍沢を一気に下り、槍沢ロッヂに到着です。槍沢ロッヂで少しの休憩をとり、また11kmの上高地街道を戻ります。
今回の槍ヶ岳登山は、天気に恵まれました。しかし、今年の夏の異常な暑さは、山でも感じました。登山道でも山小屋でも、暑かったです。それでも、憧れの槍ヶ岳に登れて幸せです。