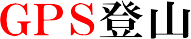富山県と長野県にまたがる北アルプスの鹿島槍ヶ岳は、後立山連峰の盟主と言われています。昨年9月に五竜岳山頂や遠見尾根から眺めた山容は、黒部川を挟んで対峙する立山や剱岳に引けを取りませんでした。南峰と北峰を吊り尾根で結ぶ山頂を見たとき、是非登ってみたいと思ったものです。
登山口は最短コースの赤岩尾根や、五竜岳からの縦走コースもありますが、今回は登りが楽といわれる柏原新道から爺ヶ岳経由で冷池(つべたいけ)山荘泊、一泊二日の日程です。
自宅を8月4日午後1時30分出発~圏央道海老名IC~中央道安曇野IC~国道147号線~県道45号線(大町アルペンライン)で扇沢無料駐車場に午後6時30分頃到着。車中泊後、翌朝5時の出発です。
扇沢に架かる鉄橋を渡り左折すると、柏原新道の爺ヶ岳登山口です。
扇沢の右側をしばらく進み、さらに樹林帯の中をジグザグにゆっくりと高度を上げていきます。開けた所から時々見えていた扇沢駅が小さくなり、岩小屋沢岳が見えてきたら石の積まれた「ケルン」に到着です。そこからは種池山荘の赤い屋根が稜線上に小さく見えますが、種池まで4.5km(3時間半)の表示があるので、まだまだ先は長いようです。爺ヶ岳山腹の緩やかな道を種池山荘目指して登って行きます。
雪の残る沢を渡り、どれも真っ直ぐには育っていないダケカンバの林を過ぎ、富士見坂(富士山が見えるのでしょうか?)や鉄砲坂の急坂を登りきると、稜線に建つ種池山荘です。山荘の周りにはお花畑が広がっています。
種池山荘のベンチで休憩後、爺ヶ岳へ向かいます。
爺ヶ岳の名前の由来は、春の雪解けの頃に現れる「種まき爺さん」の雪形からついたそうです。昔から苗代に種をまく時期の目安にしている雪形で、鹿島槍ヶ岳の「鶴と獅子」の雪形と共に長野県大町市内からも見る事が出来る代表的な雪形だそうです。春先には雪形ウオッチングもあるそうで、是非一度は参加してみたいです。
爺ヶ岳には南峰・中峰・北峰と三つのピークがあり、最高地点は三角点のある中峰です。
天気が良ければ目の前に鹿島槍ヶ岳の雄姿が広がっているはずなのですが、残念ながら山頂を望む事はできません。
爺ヶ岳中峰からは、北峰の巻道に進みます。
ハイマツの間のゆるやかな下りから、砂地の稜線に出て赤岩尾根分岐の冷乗越まで来ると、冷池山荘はもうすぐです。
2日目
朝4時起床。今日は山頂を往復し扇沢まで戻るので、早めに出発します。
朝食は山荘で弁当を作ってもらいました。ハイマツの中のテント場を過ぎると、花の多い稜線歩きです。顔を出した太陽に絶景を期待したのですが、雲は停滞したままで布引山から上は見えません。
布引岳のピークから上るにつれて風がさらに強くなってきました。霧雨の為、視界が悪く山頂は見えません。天気が良ければ楽しい稜線歩きでしょうに、残念です。ジグザグについた道をハイマツや岩影など風の少ない所で休憩をとりながら、やっと鹿島槍ヶ岳最高地点の南峰に到着しました。
南峰から北峰へは往復で約1時間位かかります。帰りは稜線の両側に咲く、高山植物を見ながらゆっくりと下ります。黒部側より信州側のほうが花の種類が多い様です。
帰りの冷乗越からのパノラマです。

冷乗越のパノラマ(左より爺ヶ岳南峰、岩小屋沢岳、立山、剱岳、毛勝三山、牛首山
花の種類が豊富です。砂礫地では高山植物の女王コマクサが咲いていました。
<< ヒメヒャクリコウ >>
イブキジャコウソウ(別名ヒャクリコウ)の葉の表面に毛があるものがヒメヒャクリコウなのだそうです。
端正な双耳峰を持つ鹿島槍ヶ岳ですが、今回は一日目から山頂が雲で覆い隠されていて、残念ながらその姿をみる事ができませんでした。是非もう一度登ろうと思います。