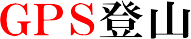南アルプスの光岳は、山頂の南西直下に光石(てかりいし)と呼ばれる石灰岩の岩峰があり、その岩が夕日に照らされると白く光って見えるところから光岳(てかりだけ)と呼ばれるようになったと言われています。
ハイマツの南限(世界最南端の自生地)で、ライチョウの生息地の南限でもあるそうです。
今回は長野県側の標高880mの易老渡(いろうど)から登ります。
自宅を前日の午後10時出発~圏央道海老名インター~中央高速飯田インター~国道151号~国道418号~国道152号~市道142号~易老渡駐車場に午前4時30分頃到着。
易老渡駐車場近くの遠山川に架かる鉄橋が登山口です。橋を渡ると標高差約1500mの厳しい登りが易老岳(2345m)まで続きます。
気温と湿度が高くつらい登りでしたが、ようやく易老岳山頂に着きました。山頂から三吉平までは緩い下りです。登山道脇やシラビソの林の地表を埋め尽くしている、シダの緑がとてもきれいです。
三吉平からはまた登りです。標高差300m程ですが、易老岳の登りで疲れた身体には、苦しい登りになりました。それでも高山植物の花々に励まされながら、今日の宿泊予定の県営光小屋を目指します。
光小屋で食事を頼めるのは50歳以上で3人以下のグループ、さらに15時までに宿泊手続きを取らないといけません。残念ながら15時には間に合いませんでした。万一の時の為に用意したカップラーメン等で夕食を済ませる事になりましたが、雨に降られる事もなく無事に小屋までたどり着く事が出来て良かったです。
2日目朝4時起床。
光岳からは残念ながら日の出をみる事はできません(イザルヶ岳からは見れるそうです)が、朝焼けの空に富士山が望めます。
5時に小屋の温かい朝食を頂き、ザックを置かせてもらって往復15分の山頂へ向かいます。
山頂は木々の中にあり展望は望めませんが、すぐ近くに西側の開けた岩の展望台があります。この辺り(1.115ha)は「大井川源流部原生自然環境保全地域」として保護されていて、動植物や土石の採集はもちろん落葉や落枝を拾うことも禁止されています。
名前の基になった光石へは7分との標識がありますが、急な下りなので往復では20分位かかります。
光小屋に戻り、帰路につきます。昨日はガスがかかっていたセンジヶ原もすっきり晴れて、振り返ると光岳や光小屋が良く見えます。分岐にザックを置いてイザルヶ岳へ、往復で15分位です。イザルヶ岳は展望がよく、中央アルプスの空木岳や木曽駒ヶ岳も望めます。南限のハイマツが山を包む様に生えていて見事です。
イザルヶ岳山頂からのパノラマです。

イザルヶ岳のパノラマ(左より光岳、空木岳、木曽駒ヶ岳、奥茶臼山、大沢岳、兎岳、聖岳、上河内岳、茶臼岳)
行きには見えなかった山も、帰りには姿を現してくれました。
 三吉ガレより恵那山(中央奥)
三吉ガレより恵那山(中央奥)光岳で見つけた花です。キノコの種類も多いです。
光岳は2600mにも満たない山ですが、山小屋までの距離が長く難易度の高い山でした。今回の山で出合った人の多くは、赤石岳や聖岳と合わせて登っていました。