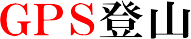南アルプスのほぼ中央に位置する塩見岳は、その西側にある塩泉の湧く、大鹿村の鹿塩集落からその名が付いたそうです。
中央自動車道の松川インター~県道松川大鹿線~国道152号線~鳥倉林道と乗り継ぎ、越路の駐車場に到着です。しかし、そこから鳥倉登山口までは約50分ほど舗装された林道歩きです。
バスだと1日2回(夏季だけ)伊那大島から登山口まで行けるようです。越路の駐車場にもバスの停留所がありました。
1日目は、塩見小屋を目指して出発です。

鳥倉登山口

桟道が多く続く

樹林帯の中を・・・

水場で一休み

滑りやすい桟道
カラマツの林の中を、ザレ場、滑りやすい桟道を何回か渡ります。
三伏峠は日本で一番高い峠で、昔は伊奈からこの峠を越えて,甲州にでる伊奈街道があり、かなりの往来があったようです。

豊口山分岐
豊口山分岐。塩川ルートとの合流点。私達の登った日は、通行止めになっていました。
分岐点を過ぎると三伏(さんぷく)峠はすぐそこです。

もうすぐ三伏峠

水洗トイレのある三伏峠小屋

ほぼ中間点の三伏峠

左が塩見岳、右は鳥帽子岳へ
三伏峠小屋のテント場を過ぎ、鳥帽子岳への道を右にみながら分けて行くと、三伏山に到着です。

三伏山山頂(2615m)

三伏山付近からの塩見岳。左側の稜線を登ります。

本谷山山頂(2658m)

ようやく塩見小屋に到着

塩見小屋付近
予約の必要な、塩見小屋は満員でした。
塩見小屋では、携帯トイレが配られました。使用済みのは小屋で処分してくれたので、快適なトイレタイムでした。
2日目早朝、ザックを小屋に置かせてもらい、弁当にしてもらった朝食を持って、山頂を目指します。

早朝、塩見小屋を出発

小屋のすぐ横から登ります

朝日が山頂付近に

朝日に輝く塩見岳を望む

塩見岳はまだか・・・

雲海が発生
時々さす朝日に、山頂の眺望を期待していたのですが、残念ながら360度のパノラマを眺めることができませんでした。

塩見岳(西峰)山頂(3046.9m)
塩見岳は、西峰(3046.9m)、東峰(3052m)からなっているが、三角点のある西峰が塩見岳の最高点に登録されている。(標高差は5.1m)

塩見岳(東峰)山頂(3052m)

東峰から西峰へ

塩見岳(左 西峰、右 東峰)
花の百名山でもある塩見岳は、花の種類も多く、可憐な花々が咲き誇っていました。

ニョホウチドリ(女峰千鳥)

ギンリョウソウ(銀竜草)

ミヤマコウゾリナ(深山髪剃菜)

タカネコウリンカ(高嶺高輪花)

ハクサンシャクナゲ(白山石楠花)

イワツツジ(岩躑躅)

ミヤマダイコンソウ(深山大根草)

キンバイソウ(金梅草)

イワツメクサ(岩爪草)

イワギキョウ(岩桔梗)

シコタンソウ(色丹草)

イワベンケイ(岩弁慶)

タカネツメクサ(高嶺爪草)

ハクサンイチゲ(白山一花)

タカネシオガマ(高嶺塩竈)

ミヤマオダマキ(深山苧環)

シロウマオウギ(白馬黄耆)

チシマゼキショウ(千島石菖)

マルバダケブキ(丸葉岳蕗)

バイケイソウ(梅蕙草)
今まで登った山ではコバイケイソウが多かったのですが、塩見岳はバイケイソウの多い山でした。

タカネグンナイフウロ(高嶺郡内風露)

ツマトリソウ(端取草)

ゴゼンタチバナ(御前橘)
塩見岳の下山の途中、早朝の暗い中では発見できなかった赤色チャートや塩見小屋までの稜線が雲の合間に出現した。

天狗岩付近

赤色チャート(赤膚の岩)
<<赤色チャート>>
天狗岩付近に鉄分を含む微細な粘土が混じった真っ赤なチャートが見られます。

塩見小屋への足取りは軽く

下山の途中、塩見岳を望む

ハイ松の続く山道
鳥倉登山口から駐車場に戻る途中、蝶を捕っては放している人に出会いました。なぜか聞いてみると、アサギマダラの観察をしているとの事です。アサギマダラは、春は北上し、夏は標高1000m位の涼しい高原で繁殖し、秋は南下を繰り返す「渡り鳥」ならぬ「渡りチョウ」だそうです。気流に乗って、遠く九州や沖縄、台湾にまで移動するとの事です。「アサギマダラを調べる会」という会があり、日本全国で130人以上の会員の方がアサギマダラの観察を続けているそうです。

鳥倉林道をひたすら歩く

マーキングされたアサギマダラ
<<アサギマダラ>>
羽が薄い浅葱(あさぎ)色のまだら模様で、そこから付いた名前だそうです。
私たちの山行は、自宅を深夜に出発し早朝から登り始めます。今回の塩見岳は前日の睡眠不足のせいか、「足がつる」というアクシデントにみまわれ、1日目は苦しい登りになってしまいました。やはり体調は整えておかなければと、反省しています。