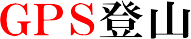長野県と岐阜県の県境に立つ乗鞍岳は、北アルプスの最南端に連なる巨大な独立山塊です。
その姿が馬の鞍に似ていることから古くは「鞍ヶ嶺」と呼ばれ、それが乗鞍岳になったようです。
剣ヶ峰を主峰に23の峰と火口湖やせき止湖など多くの湖があります。
標高2,702mの畳平まで車道が伸び、最も楽に登れる3,000m峰です。
圏央道~中央道~長野道~松本インター~国道158号で乗鞍観光センターの駐車場
乗鞍岳は平成15年からマイカー規制が実施されている為、シャトルバス(50分)で畳平へ。
乗鞍観光センターから出発する御来光シャトルバスが早朝4時10分にあると知り、早めに出発。
寒い中を待っていたのですが、前日の大雨の影響で道路状況が確認できないためと中止になりました。残念ながら御来光は拝めません。
通常の6時10分発のシャトルバスで畳平に向かいます。
畳平の乗鞍本宮中之社でお参りし、広い緩やかな道を歩きだします。
肩ノ小屋の横にある剣ヶ峰口に入ると砂礫の道になり、傾斜もだんだんと増していきます。
摩利支天岳山頂には乗鞍観測所(旧国立天文台の乗鞍コロナ観測所)が建っています。
蚕玉岳(こだまだけ)から山頂はもうすぐです。
乗鞍岳山頂には岐阜県側に「朝日権現社」、長野県側「乗鞍本宮(鞍ガ峰神社)奥宮」の2社が背中合わせに建っています。
二つの社が建つ狭い山頂で、順番待ちで記念写真をとり早々に下山します。
登る時とはまた違う景観を楽しみながら、慎重に下ります。
帰りは、富士見岳と大黒岳の山頂を踏んでバスターミナルへ戻ります。

大黒岳山頂からのパノラマ(左より高天ヶ原、剣ヶ峰、蚕玉岳、朝日岳、富士見岳(中央手前)、摩利支天岳)
火山帯の乗鞍岳のお蔭で、乗鞍高原には温泉がたくさんあります。
駐車場近くの休暇村乗鞍高原で、ゆっくりとお湯につかり帰路に着きました。